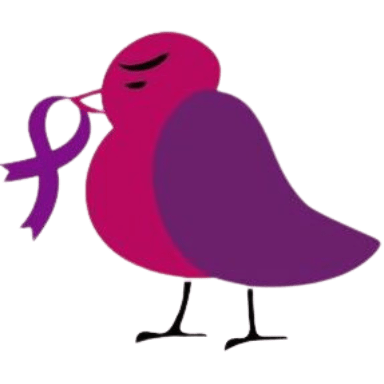国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、国連が設置している女性差別撤廃条約の実施状況を監視する委員会です。2024年9月にスイス・ジュネーブで行われたCEDAWについての報告です。
今回初めて、DVに取り組む弁護士さん達、被害当事者の方々などが、
・日本のDV被害者対策がいかに貧弱なのか
・いかにシングルマザーの貧困が深刻なのか
・日本では協議離婚が主で、単独親権について誤解に基づいた海外からの「共同親権にせよ」 との圧力があること
・面会交流などでDVや虐待がなかなか家庭裁判所でも考慮されないこと
など、レポートを作成・英訳し提出しました。
その結果、10月に委員会から日本へ
・裁判所の問題
・DV被害者支援が弱いことについて
の勧告や、「懸念をもって留意」としての指摘がされました。
報道ではあまりとりあげられていませんが、実は「裁判官にジェンダー研修をせよ」、「DV被害者対策」などについても言及されています。
詳細はこちらのサイトをご覧ください。2つの団体のレポートです(日本語版もあります)。
「DV虐待を許さない弁護士と当事者の会」国連女性差別撤廃委員会が画期的な勧告を発表
勧告全体の日本政府の仮訳もこちらで読めますが、主に暴力や結婚関係のところを以下にご紹介します。
_領土外における国家の義務_
日本企業による第三国の採掘セクターへの投資が締約国の領土外の義務と矛盾しないことを確保するためのメカニズムを導入すること、及び、それらのセクターの女性労働者がジェンダーに基づく暴力及び搾取から保護されることを確保するためのメカニズムを導入することを勧告する。
_女性に対するジェンダーに基づく暴力 _
委員会は、レイプに関する法律を改正した締約国の努力を認める。しかしながら、レイプについての一般的規定の下で配偶者間のレイプを起訴することは可能であるものの、配偶者間レイプが別個の罪として明示的に犯罪化されていないことを遺憾に思う。委員会はさらに、以下の点に懸念をもって留意する。
(a)ドメスティック・バイオレンスの被害者のためのシェルターと相談サービスの資金と人員不足の報告。
(b) 2023年の配偶者暴力防止法改正により保護命令の有効期間が6か月から1年に伸長されたところであるが、その期間が切れると女性は繰り返されるジェンダーに基づく暴力の被害を受けるおそれがあること。
(c)ジェンダーに基づく暴力の被害者に対する支援サービスへのアクセスが、農山漁村女性や、民族的マイノリティ女性、移民女性、障害のある女性やレズビアン、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックスの女性など、交差的な差別に直面している女性にとって特に困難であるとの報告、また移民女性は、出入国管理及び難民認定法の下で保護されるための資格を維持するために「正当な理由」を提出する必要があるため、在留資格を取り消されることを恐れて、ジェンダーに基づく暴力の事例を報告することに特に消極的であるとの報告。
(d)沖縄の軍事基地にいる米軍人による女性に対するジェンダーに基づく暴力。
勧告 締約国が刑法を改正して配偶者間レイプを別個の罪として明示的に犯罪化し、配偶者間レイプの犯罪性について啓発キャンペーンを実施することを勧告する。
さらに
勧告
(a)ドメスティック・バイオレンスの被害者のためのシェルターや相談サービスへの適切な資金の配分などを通して、女性に対するジェンダーに基づく暴力の被害者の保護を提供する目的で、資源の不足ギャップに対処すること。
(b)ジェンダーに基づく暴力の被害者である女性の再被害を防止するため、保護命令を延ばす手続を効率化すること。
(c)女性に対するジェンダーに基づく暴力のサバイバーに対して、農山漁村地域も含め、支援サービスやシェルターを提供又は十分に資金援助し、農山漁村女性、障害のある女性、移民女性など、あらゆる多様性を持つ女性のニーズに完全に適合し、アクセス可能なものにする。また、保護のための「正当な理由を示すという要件」が法律から明確に削除され、在留資格に関わらず被害者を保護することを確保すること。
(d) 沖縄における性暴力その他の紛争関連のジェンダーに基づく暴力の被害女性・女児に関し、予防、捜査、加害者の訴追・処罰、被害者への補償のための適当な措置をとること。
_人身取引と売買春による搾取 _ 勧告のうち 一部引用
(b)人身取引や性的搾取の被害者である女性及び女児がシェルターや法的サービスを利用する際の障壁をなくす。これには、言語的な障壁に対処することや、一時的な在留の許可を与えること、再統合のための支援を強化することなどが含まれる。
(c)独立した、秘密厳守の、ジェンダーに配慮した苦情申し立て手続の確立と労働分野における監査の強化を通じて、女性による労働搾取の報告を奨励し、人身取引の事例が効果的に捜査され、加害者とその共犯者が訴追され、適切に処罰されるようにする。
(d)子どもの搾取、特にオンライン上の搾取と闘い、児童買春やポルノ関連犯罪を防止するための対策を強化する。
_教育_ 勧告のうち 一部引用
(c)早期妊娠や性感染症を予防するための責任ある性行動を含む、年齢に応じた包括的な性に関する指導が、定期的な授業の提供を通じて、また、その内容と使用される用語に関して政治家や公務員が干渉することなく、学校の教育課程に適切に組み込まれることを確保すること。
_労働_ 勧告の内の一部引用
(h)裁判官に対し、雇用差別や雇用におけるジェンダーバイアスに異議を唱える際の条約及びその活用について研修を行うこと。
_健康_ 勧告のうち一部引用
(c)法律を改正し、人工妊娠中絶を求める女性に対する配偶者同意の要件を削除すること。
(e)全ての女性が自発的な不妊手術サービスにアクセスできるようにするために、母体保護法を改正し、配偶者同意の要件を廃止すること。
_結婚と家族関係_
委員会は懸念をもって以下について留意する。 (一部引用)
(a)民法の規定が遵守されていないため、資産の管理、銀行口座や不動産の名義へのアクセス、離婚手続における財産の平等な分割において、女性にとって困難が生じること。
(b)現在の協議離婚制度の下では、家庭裁判所は、虐待的な父親が関与するケースであっても、また保護命令を出すべきケースであっても、子どもの面会権を優先することが多く、子どもと被害者である親の両方の安全が損なわれる可能性があるとの報告。
勧告
(a)離婚手続において平等な財産分与を可能にするため、民法の規定の遵守を確保するための措置を講じること。
(b)離婚を求める女性に利用しやすい料金で法的助言を提供し、子どもの親権と面会交流権を決定する際にジェンダーに基づく暴力に十分に配慮することを確保するため、裁判官と児童福祉司の能力開発を強化・拡大すること。
(c)十分な数の安価な保育施設の供給や柔軟な勤務形態の実現を通じて、仕事と家庭生活の両立を促進することを含め、シングルマザーに対する支援を行い、シングルマザーをめぐる性差別的な固定観念を排除することに特化した措置を採用すること。
(d)同性婚、国際私法に基づいて締結された婚姻及び登録された婚姻を認め、同性婚又は事実婚の女性による養子縁組を認めること。